新築住宅を建てる際、快適な住まいを実現するために重要な要素の一つが断熱性能です。
断熱性能は、室内の温度を安定させ、光熱費の削減やヒートショック対策にも大きく関わってきます。
しかし、断熱性能を表す「断熱等級」には様々なレベルがあり、どれを選べば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
今回は、新築住宅の断熱性能の違いについて、分かりやすくご紹介します。
目次(クリックできます)
新築の断熱性能の違いを徹底比較
断熱等級とは何か?等級ごとの性能差
断熱等級とは、住宅の断熱性能を示す指標です。
数字が大きいほど断熱性能が高く、室内の温度変化が少なくなり、快適な住環境を実現できます。
等級は1~7まであり、2022年10月には6と7が新設されました。
2025年以降は断熱等級4以上、2030年以降は等級5以上が新築住宅の義務化が予定されています。
等級を上げるには、高性能な断熱材や高度な施工技術が必要となり、費用も増加します。
断熱等級4~7の比較!UA値・ηAC値を分かりやすく解説
断熱等級は、UA値(外皮平均熱貫流率)とηAC値(冷房期の日射熱取得率)によって定められます。
UA値は、建物の熱の出入りしやすさを表し、値が小さいほど断熱性能が高いことを示します。
ηAC値は、冷房期の太陽熱の侵入量を表し、値が小さいほど冷房負荷が軽減されます。
地域区分によって基準値が異なるため、ご自身の地域区分を確認する必要があります。
各断熱等級のメリットとデメリットを比較検討
・断熱等級4
省エネ基準を満たしますが、より高い断熱性能を求める場合は、他の等級を検討する必要があるでしょう。
メリットは費用が比較的安価であることです。
デメリットは、他の等級と比較して断熱性能が低いため、光熱費削減効果や快適性はやや劣ります。
・断熱等級5
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準を満たし、光熱費削減効果が高いです。
また、補助金制度の対象となる可能性があります。
メリットは省エネ効果が高く、快適な住環境を実現できることです。
デメリットは、断熱等級4と比較して建築費用が高くなります。
・断熱等級6
HEAT20 G2レベルに相当し、より高い断熱性能を備えています。
冬季の室温を確保しやすく、快適な室内環境を維持できます。
メリットは、さらに高い省エネ効果と快適性を実現できることです。
デメリットは、建築費用がさらに高くなります。
・断熱等級7
HEAT20 G3レベルに相当し、最高レベルの断熱性能を誇ります。
極めて高い省エネ効果と快適性を提供しますが、費用も最も高くなります。
メリットは、最高レベルの快適性と省エネ効果が得られることです。
デメリットは、建築費用が最も高額になります。
断熱性能向上による光熱費削減効果と費用対効果
断熱等級を上げることで、光熱費を削減できます。
削減効果は等級によって異なり、等級4から5に上げると約20%、4から6に上げると約30%、4から7に上げると約40%の省エネ効果が期待できます。
ただし、断熱等級を上げるには費用がかかります。
初期費用と光熱費削減効果を比較検討し、長期的な費用対効果を考慮して等級を選択することが重要です。

新築住宅における断熱性能向上のためのポイント
断熱材の種類と選び方
断熱材には、グラスウール、ロックウール、発泡ウレタンなど様々な種類があります。
それぞれの特性を理解し、家の構造や予算に合わせて適切な断熱材を選ぶことが重要です。
窓の種類と断熱性能への影響
窓は熱の出入りが最も大きい箇所です。
高断熱の窓を選ぶことで、断熱性能を大きく向上させることができます。
複層ガラスやトリプルガラス、高性能な窓枠などを検討しましょう。
気密性と換気システムの重要性
断熱性能を高めるためには、気密性も重要です。
気密性を高めることで、室内の温度を安定させ、省エネ効果を高めます。
同時に、適切な換気システムを導入することで、室内の空気の質を保ち、結露などを防ぐ必要があります。
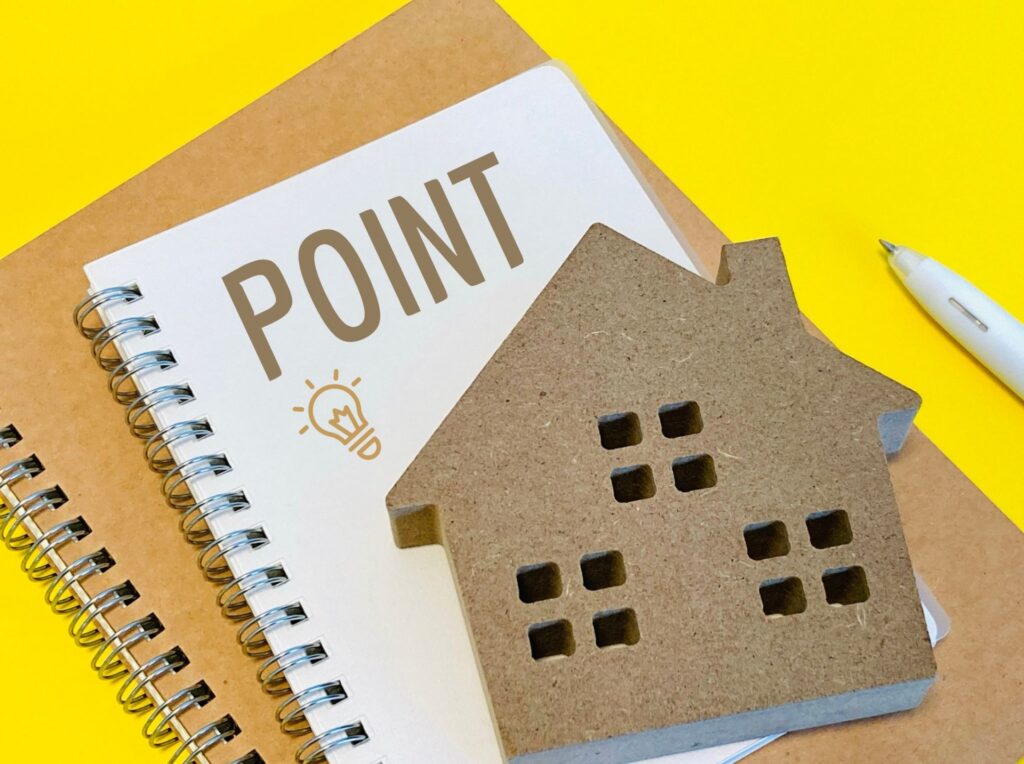
まとめ
本記事では、新築住宅の断熱性能について、断熱等級4~7を比較しながら解説しました。
断熱等級を上げることで、光熱費削減、快適性向上、ヒートショック対策など多くのメリットがありますが、建築費用も高くなります。
ご自身の予算やライフスタイルに最適な断熱等級を選択することが重要です。
断熱材、窓、気密性、換気システム、建築会社選びにも注意を払い、快適で省エネな住まいを実現しましょう。
断熱性能は、住まいの快適性と経済性を左右する重要な要素です。
しっかりと検討し、後悔のない家づくりを進めてください。











