昨晩、原因不明の嘔吐感に苦しみました。
夜中にトイレに駆け込むこと5回・・・
朝から食べ物も受け付けず、午前中は出社できませんでした。
午後からはなんとなく良くなってきましたが・・・一体なんだったのだろう・・・?
加工場に杉の丸太が搬入されました。
これから皮むき、加工、乾燥工程を経て、鹿児島での不燃材注入となる予定です。
受け入れ検査に、、、
含水率検査を行なったところ・・・辺材部は3ヶ月間の葉枯らし乾燥期間のお蔭で25%程度ですが、心材部はメーター振り切れ・・・
いわゆる『ジュクジュク』な状態。
さて、、、どこまで乾燥が進むか楽しみです。



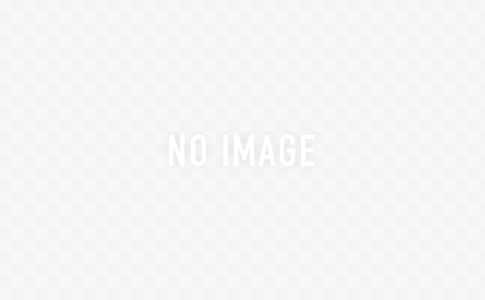
SECRET: 0
PASS:
原因不明の嘔吐感ですか...ヤバイっすね。
何か変なモノ食べたとか?大丈夫なんですか?
3ヶ月間の葉枯らし乾燥期間で25%程度ってことは、心材部はあとどのくらい乾燥させればいいんですか?
加工しながら乾燥するんですか?
まったく分からないんで、質問したくなりました。
SECRET: 0
PASS:
含水率は材木屋との打合せの言葉で測定しているとこは初めて見ました。今月から重要文化財の保存修理工事の担当になって、丁度監理者から畳の保存の輪木も13%程度の物を使うように指示され、そんな材料を右から左に入れれるはずもなくイライラしているテーマです。話は、変わりますが4/26の夜飯は渋谷でもいいかな?
SECRET: 0
PASS:
おっさんになってきたら、あっちこっちにガタがきはじめてます・・・(^^;;
木材の乾燥ですが、通常は葉枯らしで半年程度、その後数ヶ月おいて製材(板木)、さらに桟積自然乾燥で、、、詳しくは調べてみないとわからないけど、自然乾燥で建築材として安定する18%前後になるまでには一年以上は軽く係るんじゃないかなぁ・・・?
今回は丸太材で使用するのと、急な話だったので皮むき→背割り加工→乾燥釜→準不燃液注入→造作加工という工程で、乾燥は強制的に乾燥させます。
強制乾燥すると・・・木材は死んだような色に・・・そして、、、おそらくすごい割れが発生します。
今回の工事では割れは隠れるのでOK・・・とお施主様から言われてます。
SECRET: 0
PASS:
佐藤秀の現場監督であれば・・・含水率測定器くらい『買いなさい!!』
多分、5~6万だったような・・・?
しかし、、、輪木に13%?
15%以下の木材であれば、湿気を吸ってあっという間に15%前後(時には20%)まで戻ります。
まぁ、輪木だったら1.5寸角(45角ね)なんかの『乾燥材』を注文すれば乾燥釜で乾燥したやつが簡単に手にはいるよ。
それでも多分15%程度だと思うが・・・(現場搬入時)
畳の含水率もその程度はあると思うのだが・・・。
夜飯、渋谷でOKです。
当日宿泊は目白に変更しました。